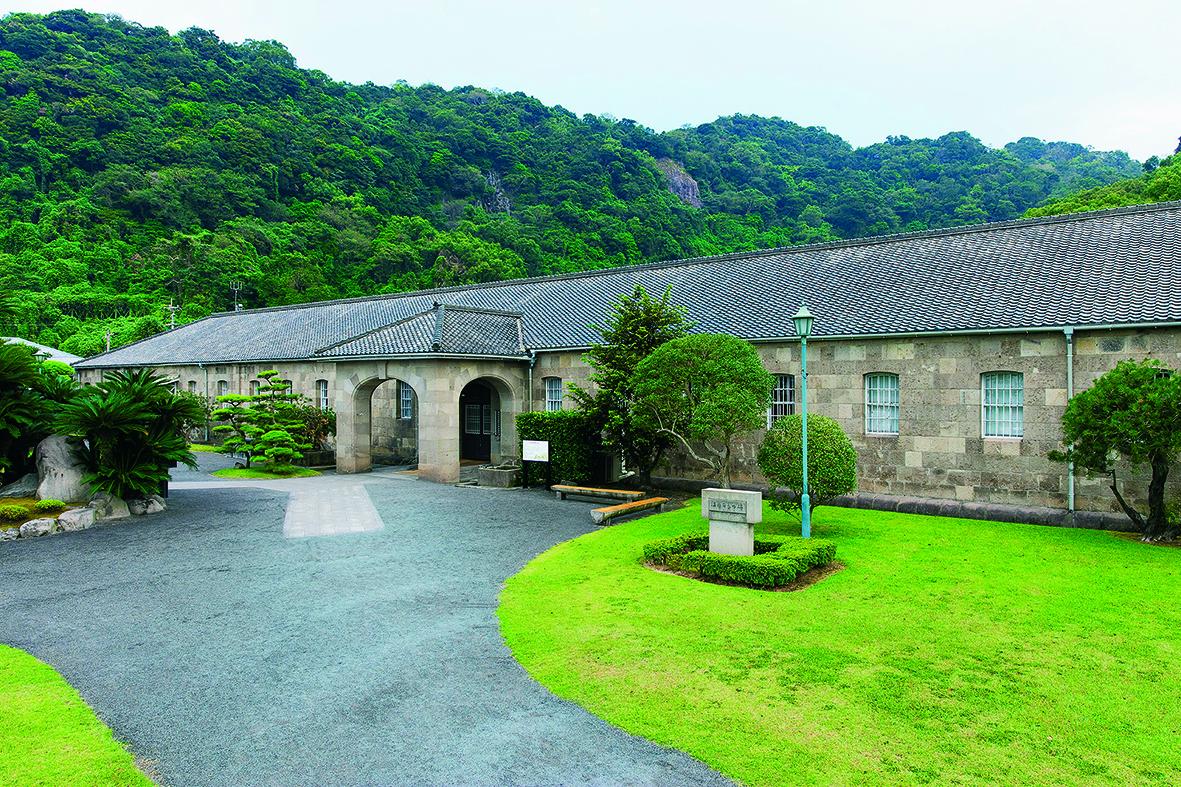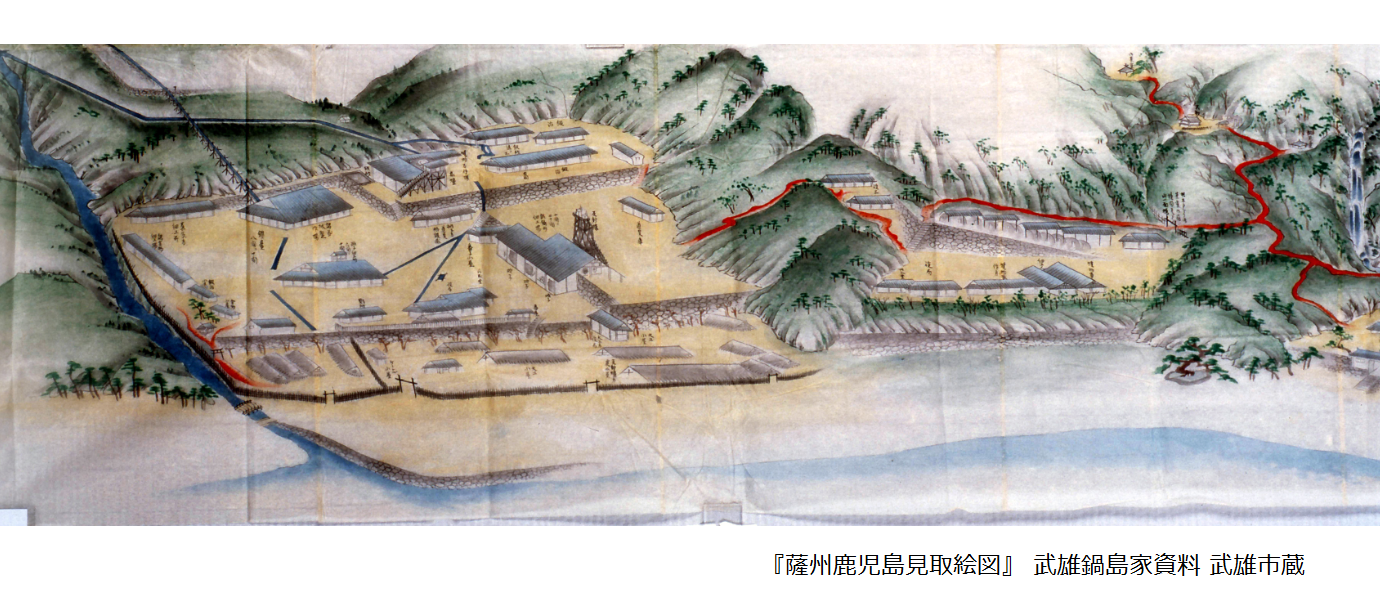-

関吉の疎水溝
集成館事業の動力! 水の取水施設
中薩摩エリア
-

金山橋
山ヶ野金山の運搬道にかけられた美しいアーチの石橋
霧島・姶良エリア
-

仙巌園
近代化事業の実験の場にもなった島津家の別邸・仙巌園
中薩摩エリア
-

反射炉跡
大砲の砲身をつくるための金属溶解反射炉
中薩摩エリア
-

沖小島砲台跡
鹿児島湾に浮かぶ 沖小島の臨時砲台跡
中薩摩エリア
-

天保山砲台跡
薩英戦争で先陣を切って 砲撃した天保山砲台
中薩摩エリア
-

寺山炭窯跡
集成館事業のための 白炭をつくった炭窯
中薩摩エリア
-

旧鹿児島紡績所技師館(異人館)
鹿児島紡績所の指導者 イギリス人技師たちの宿舎
中薩摩エリア
-

永野金山
薩摩藩が近代化を進めた金山と多くの遺産群
北薩摩エリア
-

頴娃砂鉄採取地
集成館の高炉で使用する 砂鉄を採取した海岸
南薩摩エリア
-

錫山
薩摩の近代化を支えた錫鉱山
中薩摩エリア
-

火の河原跡
馬で鉄を運搬し集成館へ供給した製鉄炉
中薩摩エリア
-

山ヶ野金山
フランス人技師を招いて近代化が進んだ大規模な金山
霧島・姶良エリア
-

佐多旧薬園
薩摩藩がつくった日本最南端の薬園
大隅エリア
-

高炉跡
大量の鉄を生産するヨーロッパ式の製鉄炉
中薩摩エリア
-

祇園之洲台場跡
薩英戦争で最も被害のあった 薩摩藩の砲台
中薩摩エリア
-

根占原台場跡
鹿児島湾の防衛のために設置 辺田海岸の砲台跡
大隅エリア
-

横山(袴腰)砲台跡
薩英戦争で火を噴いた桜島の砲台
中薩摩エリア
-

集成館ガラス工場跡
薩摩切子が生産された歴史と伝統のあるガラス工場
中薩摩エリア
-

新波止砲台跡
島津斉彬が建設 鹿児島城下の主力砲台
中薩摩エリア
-

志布志砂鉄採取地
集成館の高炉で使用する 砂鉄を採取した夏井海岸
大隅エリア
-

旧集成館機械工場
現存する日本最古の西洋式機械工場
中薩摩エリア
-

薩英戦争本陣跡(千眼寺跡)
藩主が指揮を執った薩英戦争の本陣
中薩摩エリア
-

造士館跡
あの西郷隆盛などを輩出した薩摩藩の藩校「造士館」
中薩摩エリア
-

大田発電所
串木野芹ヶ野金山のための 大田水力発電所
中薩摩エリア
-

松木弘安(寺島宗則)旧家
明治日本の近代化を牽引し不平等条約の改正に挑んだ 寺島宗則が幼少期を過ごした旧宅
北薩摩エリア
-

頴娃別府砲台跡
外国船の侵入から防衛 頴娃別府の砲台跡
南薩摩エリア
-

宮ヶ浜港防波堤
島津斉興が海商支援のため築かせた宮ヶ浜港防波堤
南薩摩エリア
-

鹿児島紡績所跡
日本初! 蒸気機関動力による ヨーロッパ式の機械紡績所
中薩摩エリア
-

久見崎軍港跡
薩摩藩が管理していた 軍港
北薩摩エリア
-

久志砲台跡
鹿児島湾の入口を防衛 久志砲台跡
南薩摩エリア
-

開成所跡
薩摩藩の近代化に貢献する人材を育成する洋学校「開成所」
中薩摩エリア
-

河野覚兵衛屋敷跡
薩摩の御用商人 河野覚兵衛の屋敷跡
南薩摩エリア
-
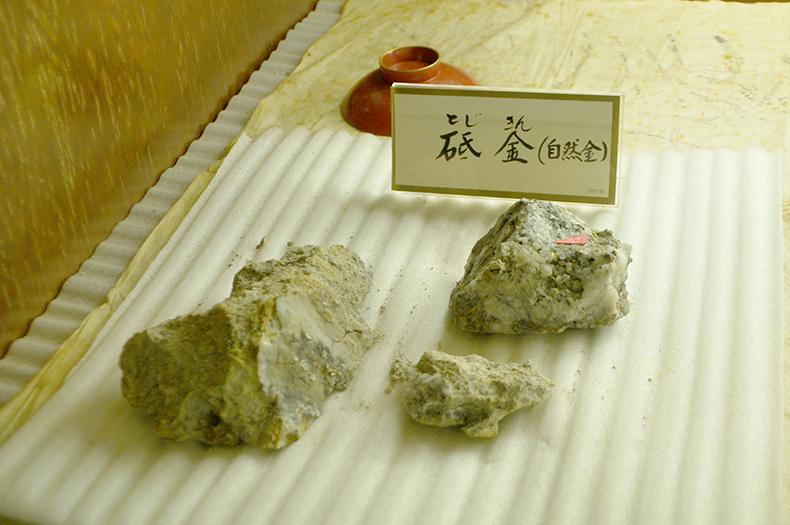
山ヶ野金山関連資料
山ヶ野金山の歴史を伝える鉱山関連の資料
霧島・姶良エリア
-

鶴灯籠
日本初のガス灯実験仙巌園にある鶴の姿の灯籠
中薩摩エリア
-

琉球館跡
薩摩藩の外交の場 貿易の拠点となった琉球館跡
中薩摩エリア
-

蘭館山
白糖製造工場を建設したイギリス人技師らの宿舎跡
奄美エリア
-

第8代濵﨑太平次の墓
薩摩の御用商人 8代目・濵﨑太平次の墓
南薩摩エリア
-

磯造船所跡
ヨーロッパ式の船を造船した磯海岸にある造船所
中薩摩エリア
-

陸軍火薬庫跡
西南戦争が勃発 きっかけは火薬倉庫
中薩摩エリア